不動産取引に携わっていると、一見オーケーそうなことがNGだったり、逆にNGそうなことが意外にオーケーだったりと、その線引きがわかりづらいと感じたことはありませんか?
そうそう時は、契約自由の原則や強行規定、あるいは特別法優先の原則など、私たち宅建業者が日頃あまり意識しない法律知識が、意外に助けになるかもしれません。
この記事では、契約自由の原則、強行規定、及び特別法優先の原則について、不動産取引目線で見ていきます。
これらを押さえたら、日々の不動産取引業務がより一層快適なものになるかもしれませんよ!
では、どうぞ。
契約自由の原則とは
私たち宅建業者が業務をする上で拠り所としている法律の一つに、民法というものがありますよね。
民法は不動産に限らず、私たち個人(あるいは会社などの法人)が、モノを貸し借りしたり、売り買いする際などに取り交わす契約などについて、様々なことを規定しています。
そんな民法ですが、実はとても重要な原則があるんです。
契約自由の原則と言います。
契約自由の原則とは、ザックリ申しますと、「契約の当事者(個人であったり法人であったり)が納得していれば、その契約の内容がどのようなものであっても、それが公の秩序や強行規定に反していなければ、それは当事者が自由に締結すればいいですよ」というものです。
そして契約自由の原則は、以下の4つの基本原則から成り立っています。
1.締結自由の原則
契約を締結するかしないかは、当事者が自分自身で決めれますよ、ということです。
不動産取引に限って言えば、賃貸借であれば貸そうとする側と借りようとする側が、売買であれば売ろうとする側と買おうとする側が、契約を結ぶかどうかを、それぞれ自分自身で決めればいいですよ、ということです。
これはわかりますよね。
2.相手方自由の原則
*相手方自由の原則については、この記事で是非言及したいことがございます。詳細は後述します。
3.内容自由の原則
金額は幾らにするか、内金あるいは手付金は何パーセントにするか、また、引渡しは何時にするかなど、その契約内容は、当事者で自由に決めればいいんですよ、ということです。
不動産取引で言えば、貸そう(売ろう)とする側の呈示額や他の契約内容に対し、借りよう(買おう)とする側の方々の中で、納得できる方いれば、その方が借りれば(買えば)いいです、そうでない方は見送ればいいです、ということです。
4.方法自由の原則
契約の方法は、当事者がちゃんと納得して合意すれば、その方法は自由ですよ、ということです。
契約書を取り交わしてもいいですし、当事者が口頭だけでいいということであれば、口頭だけでもいいです、ということです。
そしてそのことは、不動産取引についても言えます。
取引対象となる不動産が宅地で、その取引を宅建業者が仲介する場合、宅建業者は重要事項説明義務を負うので、契約書はほぼほぼ必要になってくると思われます。
しかし例えば、貸す(売る)側と借りる(買う)側が直接やりとりし、当事者同士が「契約書はいらない」というのであれば、お勧めするしないは別として、契約自体は口頭だけで成立となります。
不動産取引に見る、契約自由の原則の「2.相手方自由の原則」の例
さて上記では、契約自由の原則と、その4つの基本原則を見ました。
ここからは、その4つの中の1つ、「2.相手方自由の原則」の具体例を、不動産貸し出しの場面、及び不動産売り出しの場面にフォーカスして見て参りたいと思います。
以下の物件貸し出し方法、及び売り出し方法は、原則的にはすべてオーケーです。
サービス(設置)品付き物件の貸し出し
自ら所有する賃貸アパートの一室を貸し出そうとする方は、前賃借人から引き継いだエアコンを、サービス(設置)品として付帯させることに合意して頂ける方だけを借り手とすることができます。
アパートの一室を借りようとする方は、エアコンがサービス(設置)品となっているお部屋が嫌な方は当該物件を見送ればよく、合意できる方が借りればいい、ということです。
造作物譲渡付き事業用建物(居抜き物件)の貸し出し
自ら所有する事業用建物の一室を貸し出そうとする方は、物件内に造作物が付帯していたら、それを有償で買い取って頂ける方だけを借り手とすることがてきます。
いわゆる居抜き物件の貸し出しです。
事業用建物の一室を借りようとする方は、もしスケルトン物件等、極力造作物が付帯していない物件が希望だったら、当該物件は見送ればよく、逆に当該物件のような物件を探している方が借りればよい、ということです。
いわゆる「事故物件」の貸し出し
いわゆる事故物件ですが、難しい言葉で、「心理的瑕疵のある物件」と言ったりますよね。
さてこの、心理的瑕疵のある物件ですが、例えば、自ら所有する賃貸マンションの一室が、そうなってしまった場合であっても、その所有者は、そのことに合意して頂ける方だけを借り手とすることができます。
賃料を相場より低めに設定して募るのが一般的です。
マンションの一室を借りようとする方は、その物件に心理的瑕疵があることに合意できなければ、その物件を見送ればよく、合意できる方が借りればいい、ということです。
心理的瑕疵のある物件は、その瑕疵内容のようなことを全く気にしないタイプの方にとっては、掘り出し物の優良物件になります。
設置内装が他のお部屋と何ら変わらないのに、割安で賃借できるからです。
建築条件付き土地の売り出し
土地の所有者は、その土地上に、指定業者によって住宅を建築することに合意して頂ける方だけを買い手とするこてができます。
いわゆる、建築条件付き土地の売り出しです。
住宅用地を買おうとする方は、そのことに合意できなければその土地の購入は見送ればよく、合意できる方が購入すればよい、ということです。
既存不適格建築物の売り出し
建築基準法の改正によって、当初は適合していたけれど、その後不適合になってしまった中古戸建てがあるとします。
いわゆる、既存不適格建築物です。
既存不適格の中古戸建ての所有者は、その物件が既存不適格建築物であることに合意して頂ける方だけを買い手とすることができます。
中古戸建て、もしくは宅地を購入しようとする方は、そのことに合意できなければ購入を見送ればよく、合意できる方が購入すればよい、ということです。
(注)
なお既存不適格建築物の取引には、様々な確認事項、合意事項が発生しますが、この記事ではその詳細は割愛します。
違反建築物の売り出し
増築によって、指定容積率をオーバーしてしまい、適合しなくなった建築物があるとします。
いわゆる、違反建築物です。
実は違反建築物であっても、原則的には、その物件の所有者は、その物件が違反建築物であることに合意して頂ける方だけを買い手とすることができます。
買おうとする方が、その物件が違反建築物であることを十分に理解し、それに伴うリスク等も十分に理解した上でだったら、原則的には所有者は、その物件を売り渡すことができる、ということです。
(注)
なお違反建築物の取引には、様々な確認事項、合意事項が発生しますが、この記事ではその詳細は割愛します。
境界未確定土地の売り出し
隣接地の所有者等から協力が得られず、境界のうちの一部を確定できない土地があるとします。
実はそのような、境界の一部の確定が見込めそうにない土地であっても、その土地の所有者は、そのことに合意して頂ける方だけを買い手とすることができます。
買おうとする方が、その土地の境界の一部の確定が見込めそうにないことを十分に理解し、それに伴うリスク等も十分に理解した上でだったら、原則的には所有者は、その土地を売り渡すことができる、ということです。
(注)
なお境界の一部の確定が見込めそうにない土地の取引には、様々な確認事項、合意事項が発生しますが、この記事ではその詳細は割愛します。
強行規定とは
この記事の最初のところで、契約自由の原則とは、「当事者が納得していれば、その契約の内容がどのようなものであっても、それは当事者が自由に締結すればいいですよ」とご説明しました。
ただしこれには、「公の秩序や強行規定に反していなければ」ということでしたね。
ではこの強行規定とは、一体どういうもでしょう?
強行規定とは、「当事者の意思に左右されることなく強制的に適用される」とされている規定のことです。
契約のある部分が、強行規定に反していたとします。そうしたらその契約は、その部分について無効とされます。
これに対し、任意規定という言い方をするものもあります。
任意規定とは、何らかの法律と異なる定めをした場合、その定めのほうに優先順位を譲る法律の規定のことです。いわば「受け皿が大きい」法律の規定のことです。
さて、上記の強行規定のほうですが、不動産取引の現場では、これがどういうふうに用いられるのでしょう?
以下に見ていきましょう。
不動産取引に見る、強行規定の例
賃貸借においても売買においても、不動産取引において強行規定とさるれる規定はたくさんあります。
ごく一部ですが、具体例を見てみます。
借地借家法の強行規定の例
ある方がアパートの一室を賃借しようとして、当初の契約期間を2年とする普通借家契約を結ぼうとしています。
その賃貸借契約書の特約には、「賃貸人は正当事由が無くても3ヶ月前に申し入れれば、更新を拒むことができます」とあるとします。
さてこの特約は有効でしょうか?
もちろん無効ですよね。
期間の定めのある普通借家契約においては、借地借家法における法定更新のところは強行規定です。
上記の特約は、借地借家法における法定更新のところに反していますよね。
したがって、上記の特約は無効となります。
更に強行規定は、「当事者の意思に左右されることなく」でしたね。
よってもし仮に、このアパートを借りようとする方が、合意して契約を締結したとしても、やはり無効となります。
ところでこの「無効」ですが、不動産取引の現場においては、実際にどういうふうにその効力が現れるのでしょう?
例えば、下記のようなケースが想定できます。
今仮に、この賃貸借取引の宅建業者が、その特約が無効であることを見落としてしまい、契約が締結され、物件が引き渡されたとします。
そして2年を迎える3ヶ月前に、賃貸人様が賃借人様に、更新しない旨の通知をして来られたとします。
その時点になって賃借人様が「やっぱり更新したい」とおっしゃったとします。
一方賃貸人様は、「契約書に従って、退去してもらわなければ困る」と主張なさったとします。
しかし賃貸人様の意志はどうあれ、更新はさることになります。
このようなケースの場合、おそらく賃貸人様は、仲介をした宅建業者にその責任を求めて来られるかと思います。
私たち宅建業者は、強行規定にはくれぐれも注意しましょう!
宅建業法の強行規定の例
ある宅建業者が自ら売主として、宅建業者でない一般の個人の方に新築戸建を売り渡すことになりました。
当初3000万円で売り出していましたが、購入希望者は100万円の値引きを希望しました。
売主業者は、万が一の損害賠償の場合の予定の額を、600万円とさせて頂けるなら値引きします、と回答しました。
そして双方は、売買の代金2900万円、損害賠償額の予定の額600万円で契約を締結したとします。
この場合は、損害賠償額の予定の額600万円のうち、代金の2割を越える部分が無効になります。
宅建業法では、宅建業者が自ら売主となる場合、「損害賠償額の予定」と「違約金」との合計額は、代金の2割を超えてはならないと定めていて、これは強行規定とされています。
(注)
不動産取引において強行規定とされるものは、他にも様々あります。
特別法優先の原則とは
もう1つ、私たち宅建業者が押さえておきたい法律の原則があります。
特別法優先の原則というものです。
法律には、大きく分けて一般法と特別法というものがあります。
特別法優先の原則とは、一般法と特別法とで内容が異なっていたら、特別法のほうが優先されますよ、という原則のことです。
一般法と特別法とは、下記のようなもののことです。
【一般法とは】
広く一般的に適用される法律のことです。
私たち宅建業者にとって関係の深い一般法としては、民法がそうです。
【特別法とは】
ある特別の範囲に限定して適用される法律のことです。
私たち宅建業者にとって関係の深い特別法としては、宅建業法や借地借家法がそうです。
不動産取引に見る、特別法優先の原則の例
ではこの特別法優先の原則は、不動産取引の現場でどういうふうに機能しているのでしょう?
1つだけですが、最後にその象徴的な例を見ておくことにしましょう。
「Aさんが、自ら所有する建物を建てる目的で、Bさんから土地を借りた」
取引の対象となる土地が、建物所有を目的としていなかったら、賃貸借に関する諸規定は、民法が適用されます。
ところが上記取引は、建物所有を目的としていますよね。
建物所有を目的とする土地の賃貸借は、一般法である民法に優先して、借地借家法が適用されます。
したがって上記事例では、借地借家法が適用されることになります。
私たち宅建業者にとってこのお馴染みの原則ですが、実はこれこそが、特別法優先の原則です。
まとめ
いかがでしたか?
今回の記事で扱った内容は、日頃の業務では、あまり馴染みのない内容だったと思います。
しかし、不動産取引を重ねていくと、どこかのタイミングできっと助けになる事柄だと思いますよ!
以下にもう一度、内容を確認しておきます。
□契約自由の原則
1.締結自由の原則
2.相手方自由の原則
3.内容自由の原則
4.方法自由の原則
□強行規定
当事者の意思に左右されることなく強制的に適用される規定↔任意規定
(具体例)借地借家法:法定更新/宅建業法:自ら売主の場合の「損害賠償額の予定」と「違約金」の合計額の上限
□特別法優先の原則
特別法が一般法に優先する
一般法:民法/特別法:宅建業法・借地借家法
この記事は、以上になります。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。






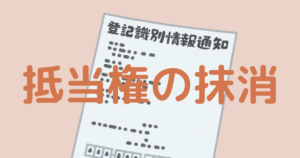


コメント